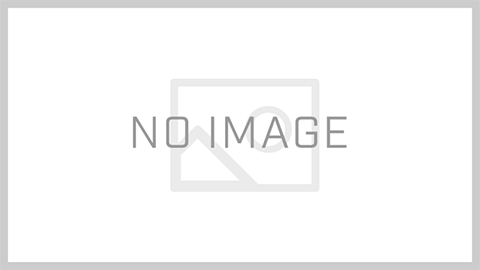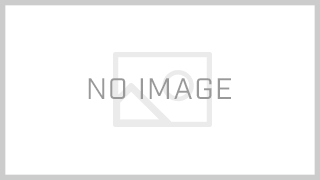量子コンピュータ 実用化 日本の最新動向と最前線企業の取り組み徹底解説
量子コンピュータの実用化が日本に与えるインパクト
量子コンピュータは、従来のコンピュータでは到達できなかった計算パワーを実現する新たな技術として世界中で注目を集めています。
日本でも、量子コンピュータの実用化に向けて官民で活発な研究開発や産業応用が進んでいます。
量子コンピュータの実用化によって、日本の産業界や社会にどのような変革がもたらされるのか、その動向や技術的な最前線について詳しく解説します。
量子コンピュータという最先端技術は、日本の経済競争力強化や新産業創出、社会課題解決に大きなポテンシャルを秘めています。
特に、製薬、物流、素材開発、金融、セキュリティといった分野では、量子コンピュータ実用化によるブレイクスルーが期待されています。
日本における量子コンピュータ実用化の現状
日本では、政府主導の「ムーンショット型研究開発制度」や「量子技術イノベーション拠点」構想を中心に、量子コンピュータ実用化に向けた取り組みが本格化しています。
東京大学をはじめとする大学や理化学研究所(理研)、産業技術総合研究所(AIST)、情報通信研究機構(NICT)などが、量子コンピュータ技術の核となる研究機関として世界的な注目を集めています。
また、日本の大手企業としてはNTT、日立製作所、東芝、富士通などが量子コンピュータのハードウェア開発やアルゴリズム研究、応用事例の構築を積極的に進めています。
近年ではスタートアップ企業のQunaSys(クナシス)やBlueqat(ブルーキャット)などが、量子コンピュータの実用化促進において存在感を強めつつあります。
先進的研究の拠点と政府の支援体制
日本政府は2020年、量子技術に関する「量子技術イノベーション戦略」を策定し、巨額の研究開発予算を投入しています。
東京大学 量子情報科学研究センター(QuICS)、理研の「量子コンピュータ研究センター」などが実用化のカギを握る最先端研究を担っています。
NECや富士通、東芝、日立製作所などは、これら研究機関と産学連携を深め、実用レベルでの量子コンピュータの開発を推進しているのが特徴です。
産業界ではNTTが、光量子コンピュータの研究で世界的に評価が高く、2021年には光子による量子計算機の試作機を発表、産業応用に道を開いています。
日本企業の量子コンピュータ実用化戦略
NTTは、光を情報のキャリアとする「光量子コンピュータ」技術でリーダーシップを発揮しています。
具体的には「時間ビン多値量子ビット」と呼ばれる独自技術を活用し、大規模化と高精度化を両立できるアーキテクチャで海外勢と差別化しています。
日立製作所は、超伝導方式による量子コンピュータ開発に着手しており、国際競争のフィールドで米国・欧州勢に迫る技術を磨いています。
さらに東芝は、量子暗号技術の実証実験にも積極的で、情報セキュリティ分野での実用化が現実味を帯びています。
富士通は量子コンピュータのエミュレーターや量子インスパイアード技術(デジタルア